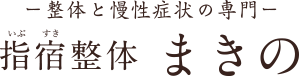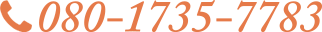先週末はオステオパシー大学の授業で神戸へ行きました。
学校はすでに4年生を迎え、時の経つ速さと授業の内容の深さに驚きます(汗)
4年生の始まりの科目は「ホルモン」を学びました。
特に、ストレスと戦う現代社会において、
体がどのように反応するのかという点を、ホルモンや自律神経の働きから学ぶことが出来ました。
今回はストレスの正体を明かしつつ、体に与える影響を考えていきます。
そもそもストレスとは?
ストレスという言葉はカナダの「ハリス・セリエ」という科学者が提唱した「ストレス概念」という言葉が中核となっています。
マウスを使った実験で、ある状態の変化に気付き、「ストレスにかかった状態」から防衛反応について考察されています。
そこでストレスとを大きく分けると
・自律神経が主にかかわる「精神的なストレス」
・ホルモンが主にかかわる「ケガや感染といった体に物理的に変化が及ぶストレス」
に分かれます。
ホルモンによるものは、動物として敵と戦い、傷を負っても治癒してくるそういった反応です。
いわゆる病院で手当てを受けられるような状態となります。

現代社会では主に、対人関係による家庭環境や職場環境といった精神的なストレスに向き合うことが多いです。
このストレスは数日から数年と続くことから、次に紹介するストレスの疲憊期に入りやすいのが特徴です。

ストレスによって体はどう反応するの?
ストレスの要因があると、警告期⇒抵抗期⇒疲憊期(ひはい)という3段階があり、
その段階を経て体に不調があられるようになります。
まず、警告期では人体の中ではそのストレスに対して戦う体制をとります。
そこでは、疲れやすくなるや寝つきが悪くなるといった症状を感じる場合があります。
しかし、この時点でストレスを解消できると大きな問題となることなく解消することが出来ます。
次に、抵抗期ではストレスを自覚しつつ、体は抵抗を示しており、
感情の起伏が激しくなったり、落ち込みやすくなったりという精神面の変化が起こります。
最後に、疲憊期に及ぶと長期間に続くストレスに対してエネルギーが消耗し
神経や筋肉ぬ語気が衰えてきます。また、うつ症状のあらわれるのもこの時期です。
ストレスと向き合うために
適度なストレスは人を成長させる要因ともなり、一概に悪いものばかりと話言えません。
しかし、精神的なストレスというのは、対人関係などのよるものがおおいため、
その環境自体をどうにかするといったことは難しいのが現状です。
だからと言って、我慢し続けると体のエネルギーを消耗するばかりで、健康とは言えません。
また、自律神経系の失調により心臓や神経にも悪影響が出てくると
様々な不調を引き起こしかねません。
ここで重要なのは、
「頑張らない勇気」を持つことです。
ストレスに悩まされる状態の人は大抵の人が真面目で頑張り屋です。
後にも先にも自分の体があってこそ、まずは自分の性格を把握してあげましょう。
そして、次に心理用語で効果てきめんな
「リフレーミング」でものを捉えるという事です。
よくコップ半分の水を見て「もう半分なのか」か「まだ半分ある」と思えるのかの気持ちが大事です。
体のメカニズムから考えても、大脳は普段からの思考のクセを無意識に再現しようとしてしまいます。
今こそ、一歩を踏み出して変わる勇気が必要となります。

オステオパシーで出来ること
ここまで、ストレスによる体の反応や普段心がけてほしい気持ちの持ち方を紹介しました。
体の不調にかかわる身体の反応は繊細で、どのようにかかわるかを考えなければなりません。
例えば、疲憊期にある精神的な症状やそれに伴う頭痛・肩こり・腰痛などの不調がある場合に、
強いマッサージや関節を鳴らされるほどの刺激は身体のエネルギーの消耗を加速させ、より重篤な症状を引き起こす可能性があります。
単なる症状だけでなく、その体の変化の段階について把握する、問診。知識。
これには、オステオパシーの考え方が非常に有効です。
ぜひ、ストレスにおいて気にあることがあれば、お気軽にご相談ください。